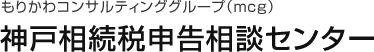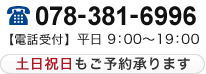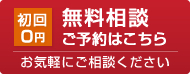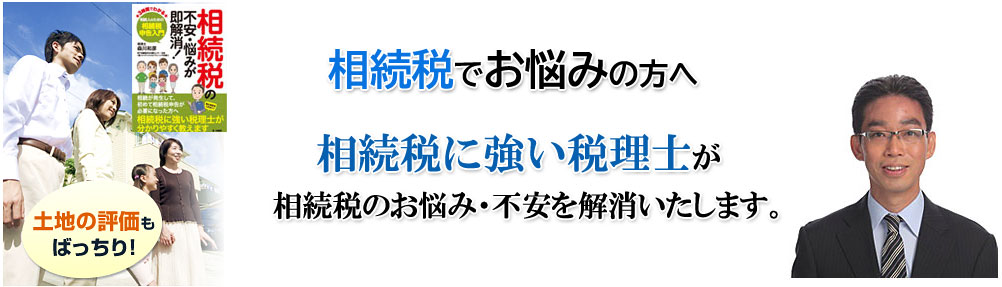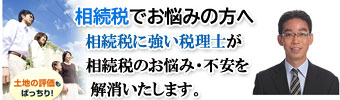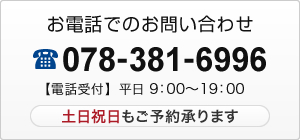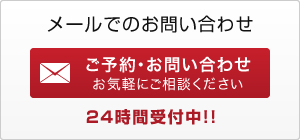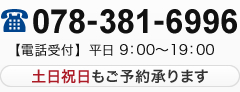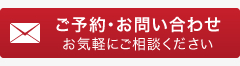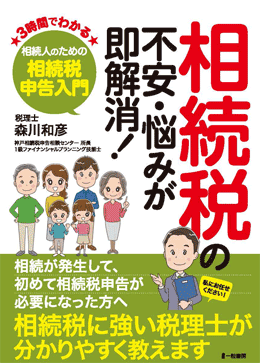![]()
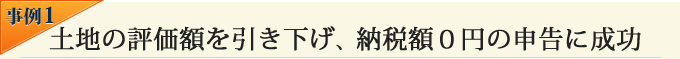
| 相続人 | 2名(長男・次男) |
|---|---|
| 基礎控除 | 7,000万円(当時:税制改正前) |
| 財産額 | 約8,000万円 |
| 納税額 | 0円 |
神戸市垂水区在住のお父様が亡くなられ、相続人が長男・次男の2人。
基礎控除が7,000万円(当時:税制改正前)であり、財産額は約8,000万円でした。
ご長男様からお問い合わせをいただき、ご面談後、相続税の申告依頼を受けました。
自宅(敷地と建物)、預金合わせて、約8,000万円あり、
小規模宅地の評価減を使えると相続税額が0円に収まるかもしれないという事案でした。
そこで、小規模宅地の要件の確認を慎重に行い、それと同時並行して名義預金や名義株の有無や他に財産のもれがないかどうかご確認をいただきました。
どちらも同居はしていなかったが、長男は賃貸暮らしで家を継いでご実家に移り住むということで特例の要件を満たし自宅敷地の430㎡中、240㎡までは80%減額し、宅地価額を18,790,720円⇒10,400,446円(▲8,390,274円減額)した。
また、未払いになっていた固定資産税や医療費の未払いも相続人が払っていたため
債務控除し、その結果、財産額約8,000万円⇒6,956万円(<7,000万円(基礎控除))に
収まりました。
小規模宅地の特例は申告が要件のため、
その旨ご説明し、
納税額が0円で喜んで頂きました。
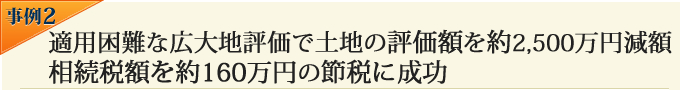
| 相続人 | 4名(配偶者・長男・次男・長女) |
|---|---|
| 基礎控除 | 9,000万円(当時:税制改正前) |
| 財産額 | 約1億5,000万円 |
| 節税額 | ▲1,610,500円 |
明石市在住のお父様が亡くなられ、相続人が配偶者・長男・次男・長女の4人。
基礎控除が9,000万円(当時:税制改正前)であり、財産額は約1億5,000万円でした。
ご長男様からお問い合わせをいただき、ご面談後、相続税の申告依頼を受けました。
ご自宅と預金、その他、父からの相続で引き継いだ上場株式、
その他、約1,300㎡の広い土地をお持ちでした。
そこで、広大地の適用を考え、要件を吟味し、現地調査も行い評価を行いました。
その結果、通常の評価では55,398,000円の評価でありましたが、
広大地の評価を
行うことで、29,585,301円に(▲25,812,699円減額)して申告を行いました。
この評価減のほか減額要素を加味して、
結果として通常の申告よりも▲1,610,500円分の節税になりました。
なかなか、この広大地の適用は困難ですが、
適用要件をしっかり確認し適用が可能な場合は
積極的に使っていくことで納税者に喜んでいただけました。
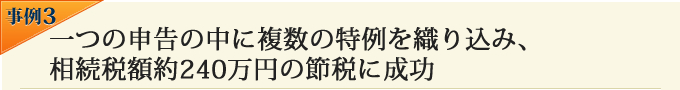
| 相続人 | 4名(配偶者・長女・次女・長男) |
|---|---|
| 基礎控除 | 9,000万円(当時:税制改正前) |
| 財産額 | 約1億4,000万円 |
| 節税額 | 約240万円 |
神戸市西区在住のお父様が亡くなられ、相続人が配偶者・長女・次女・長男・の4人。
基礎控除が9,000万円(当時:税制改正前)であり、財産額は約1億4,000万円でした。
ご長男様からお問い合わせをいただき、ご面談後、相続税の申告依頼を受けました。
この依頼者様の場合、ご長男家族がお父様と同居されていたために、
小規模宅地の評価減の適用が考えられ、また、広大な土地(約1,500㎡)を自宅以外に持たれていたため広大地の評価減の適用、また、他にも都市計画道路予定地もあったためその減額も行いました。
自宅敷地の470㎡中、240㎡までは小規模宅地の評価減の特例を使って80%減額し、
宅地価額を21,057,400円⇒12,455,229円(▲8,602,171円減額)しました。
また、広大地の評価を行うことで、
63,420,000円⇒33,263,790円に(▲30,156,210円減額)して申告を行いました。
さらに、その土地は都市計画道路予定地であったため、さらに0.9掛けで評価を行い、33,263,790円⇒29,937,411円(▲3,326,379円減額)しました。
その結果、その他の減額も加味して大幅に財産額を圧縮し、
相続税額約240万円の節税になり申告を行いました。
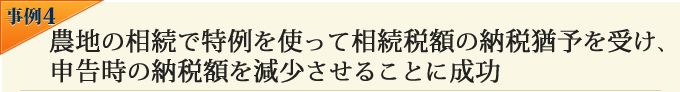
| 相続人 | 4名(お母様・長男・次男・三男) |
|---|---|
| 基礎控除 | 9,000万円(当時:税制改正前) |
| 財産額 | 約1億5,000万円 |
| 納税額 | 0円 |
加古川市在住のお父様が亡くなられ、相続人がお母様・長男・次男・三男の4人。
基礎控除が9,000万円(当時:税制改正前)であり、財産額は約1億5千万円でした。
ご長男様からお問い合わせをいただき、ご面談後、相続税の申告依頼を受けました。
ご長男様が農業をされている方で、一括で相続税が払えるぐらいだったら
納税猶予を使わずに納税したいとのことでした。
試算をしてみると、約600万円の納税額が必要になり、困難な状況でした。
そこで、20年という期間はありますが、以前と同様、農業をされていくということで、
農業委員会に適格者証明の申請を行い、現地確認を経て適格者証明をもらいました。
農地の猶予の適用を受けることで、納税額は0円になり
気が楽になったとおっしゃられました。
この依頼者様のように農業の継続意思がある方は、
納税猶予の適用も考えて一番良い方法を選択しました。